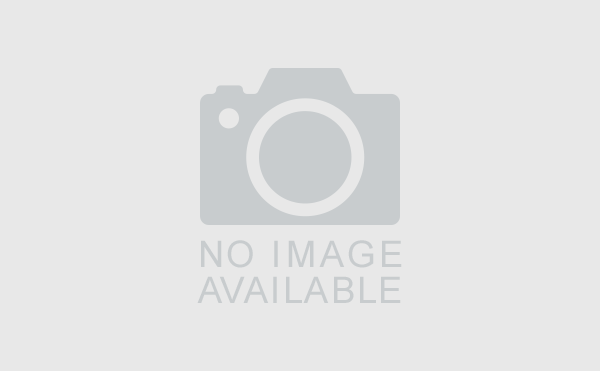本番1ヶ月前の10km走で判明!失敗しない3つの科学的戦略 no.84
こんにちは!
フルマラソン本番まで、いよいよ1ヶ月です。緊張します。
「これまでの練習は、果たして十分だっただろうか・・・」「本番で自己ベストを出すには、あと何をすればいいんだろう?」 そんな不安が入り混じる中、ソワソワした時期を過ごしています。
先日、僕が練習した10kmのペース走が、まさにそんな不安を解消する大きなヒントになりました。 ただの練習記録を、少しだけ科学的な視点で「なぜこうなったのか?」と深掘りしてみたところ、本番のレース戦略に直結する課題と対策がわかってきました。
今回は、誰でもできる「練習日誌の分析方法」と、そこから出てきた「科学的根拠に基づくレース戦略」を紹介しますね。
ある日の10kmペース走で・・・
この日のコンディションは、気温4℃で強風です。決して良い天気とは言えない日でしたが、こうした条件でのデータこそ・・自分の弱点や課題がわかってきます。
・走行距離:10.04km ・運動時間:49分14秒 ・平均ペース:4分54秒/km
そして、こちらが今回の分析のキモとなる「1kmごとのラップタイム」です。
・1km:4:49 ・2km:4:51 ・3km:4:36 ・4km:4:38 ・5km:4:42 ・6km:4:41 ・7km:4:32(最速ラップ) ・8km:4:44 ・9km:5:12 ・10km:5:22
このラップタイムの変動にこそ、パフォーマンス向上のヒントが隠されています。
ラップタイムから読み解く3つの区間・・・
【序盤:1~3km】 走り始めは体が重く感じましたが、3km目にはペースが自然と4分36秒まで上がっています。多くのランナーが経験するように、このあたりでエンジンがかかり、体がレースモードに切り替わっていくのが分かります。
【中盤:4~7km】 7km目に最速ラップ(4分32秒)を記録しました。
呼吸も楽で、脚もスムーズに動く、いわゆる「ゾーン」に入っていた状態です。この感覚で走り続けられる距離を延ばすことが、今後の練習の目標になります。
【終盤:8~10km】 最後の3kmで、ペースが5分台まで大幅にダウンしました。コース終盤の上り坂と、寒さによる体力の低下だと思います。この失速こそが、フルマラソン本番で起こりうる最悪のシナリオの練習ができました。
たった1回の練習から得られた「3つの科学的戦略」・・・
この10kmペース走のデータを「なぜ?」と深掘りすることで、本番のレース戦略に直結する3つの重要な収穫がありました。
戦略1: エネルギーの無駄遣いを防ぐ「ペース配分」の科学・・
今回のラップタイムは、典型的な「前半オーバーペース、後半失速」パターンです。 実は、マラソンで最も効率的な走り方は「イーブンペース(終始一定のペース)」か「ネガティブスプリット(後半のペースを前半より上げる)」であることが科学的に証明されています。ん〜なるほど・・・
前半にペースを突っ込みすぎると、後半に必要となるエネルギー(グリコーゲン)を先に使ってしまい、エネルギー切れを早めるだけです。つまり、前半の「貯金」は、結果的に大きな「借金」となって跳ね返ってくるのです。
本番では、序盤の興奮を抑え、いかに冷静にエネルギーを温存できるかが完走の鍵となります。
ペース管理の必須アイテム 体感だけに頼らず、正確なペースを刻むためにはGPSウォッチが不可欠です。

GARMIN(ガーミン) vivoactive 6 Black/SlateフィットネスGPSウォッチ AMOLEDディスプレイ 36gの軽量設計 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ 【日本正規品】
戦略2: 終盤の失速は根性論ではない!「エネルギー枯渇」の科学・・・
終盤に脚が動かなくなるのは、「気合が足りない」からではありません。 体内のエネルギー源である「筋グリコーゲン」がなくなり、体がエネルギー切れ状態に陥ることが科学的な原因です。
特に寒い日は、体温維持のためにより多くのエネルギーを消費するため、エネルギー切れのリスクが高まります。
今回の失速は、まさにこの状態を疑似体験したと言えます。 これを防ぐ唯一の方法が、計画的な「エネルギー補給」です。
フルマラソンでは、エネルギーが枯渇し始める30km地点より前に、定期的にジェルなどで補給を続けることが非常に重要になります。
僕のレースのパフォーマンスを左右する補給食 は以下です。

【高配合】アミノサウルスジェル エリート4個セット(ピーチレモン2個・グレープ2個)
戦略3: シューズは好みで選ぶな!「ランニングエコノミー」の科学・・・
なぜ、近年のカーボンプレート搭載シューズは、ランナーを速くしてくれるのでしょうか? それは「ランニングエコノミー(燃費)」を劇的に向上させるからです。
ランニングエコノミーとは、「同じスピードで走るために、どれだけ少ないエネルギー(酸素)で済むか」という指標ですね。
カーボンプレートが着地の衝撃を効率的に推進力へと変換してくれるため、ランナーは少ないエネルギーで、より速く!より長く走り続けられるようになります。 研究によれば、平均で2~4%も燃費が向上すると言われています。
シューズ選びは、もはやデザインや好みだけでなく、自分の走りを科学的にサポートしてくれるパートナーを選ぶという視点が不可欠です。
最新シューズで走りを良くします☆

[アシックス] ランニングシューズ S4+ YOGIRI 1013A158 ユニセックス大人 600(フラッシュ レッド/キャリア グレー) 26.5 cm 2E
走らない時間の使い方が、本番の走りを決める・・
質の高い練習はもちろん重要ですが、それと同じくらい「走っていない時間」、つまり回復と準備の質がパフォーマンスを左右します。
1. 練習のメリハリ
「速く走る日」と「ゆっくり走る日」を分ける練習法は、「分極化(ポーラライズド)トレーニング」と呼ばれ、多くのエリート選手がやっています。
練習の約8割を楽なジョギングをし、残りの2割を高強度の練習にあてています。このメリハリが、最も効率的に走力を向上させることが分かっています。
2. 補給と休養
運動後の「30分以内にタンパク質+糖質を摂るべき」という説は、これまで多く支持されてきたものの、最近の研究では「そのタイミング」よりもむしろその日の総合的な栄養バランスと睡眠の質・量が回復にとってより決定的であることがわかっています。
運動後、すぐ補給できない場合でも、運動後1〜2時間以内に十分なタンパク質(体重に応じた量)と必要に応じて糖質を補えば、筋タンパク合成や筋力アップには大きな差はないという研究が複数あります。
糖質補給は、特に持久性運動後などでグリコーゲンが枯渇している時に有効ですが、日々の糖質量を運動量に応じて調整することが大切です。
そして、最高の回復を支えるのが「睡眠」です。睡眠不足や質の悪い睡眠は、筋肉の修復を妨げ、成長ホルモンや別の回復メカニズムの働きを弱めてしまいます。
睡眠のポイントは、「なるべく毎晩一定の時間眠る」「できるだけ中断が少ない」「深い睡眠(ノンレム深睡眠)の割合を確保」すること、です。
筋肉合成率に有効な高タンパク質なプロテイン(アイソレート)

マイプロテイン Impact ホエイ アイソレート (WPI)1kg バニラ
3. レース本番を意識した刺激入れ・・
大会直前期の練習量を落とす期間を「テーパリング」と呼びます。レース1~2週間前には走行距離を半分程度に減らしつつ、レースペースでの刺激を入れることで、疲労を抜きながら体を本番モードに切り替えることができます。
自分の付けている練習日誌が、最高の戦略になる・・・
自分の感覚や経験は、大切な財産になります。
しかし、そこに少しだけ科学的な視点を加えることで、日々の練習がより戦略的で、面白いものに変わっていきます。
たった10kmの練習記録も、「なぜ?」と問いかけるだけで、本番の自分を助けてくれるヒントに変わります。
この記事が、皆さんのトレーニングのヒントになれば良いと思っています。
最後まで読んでくれて、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。